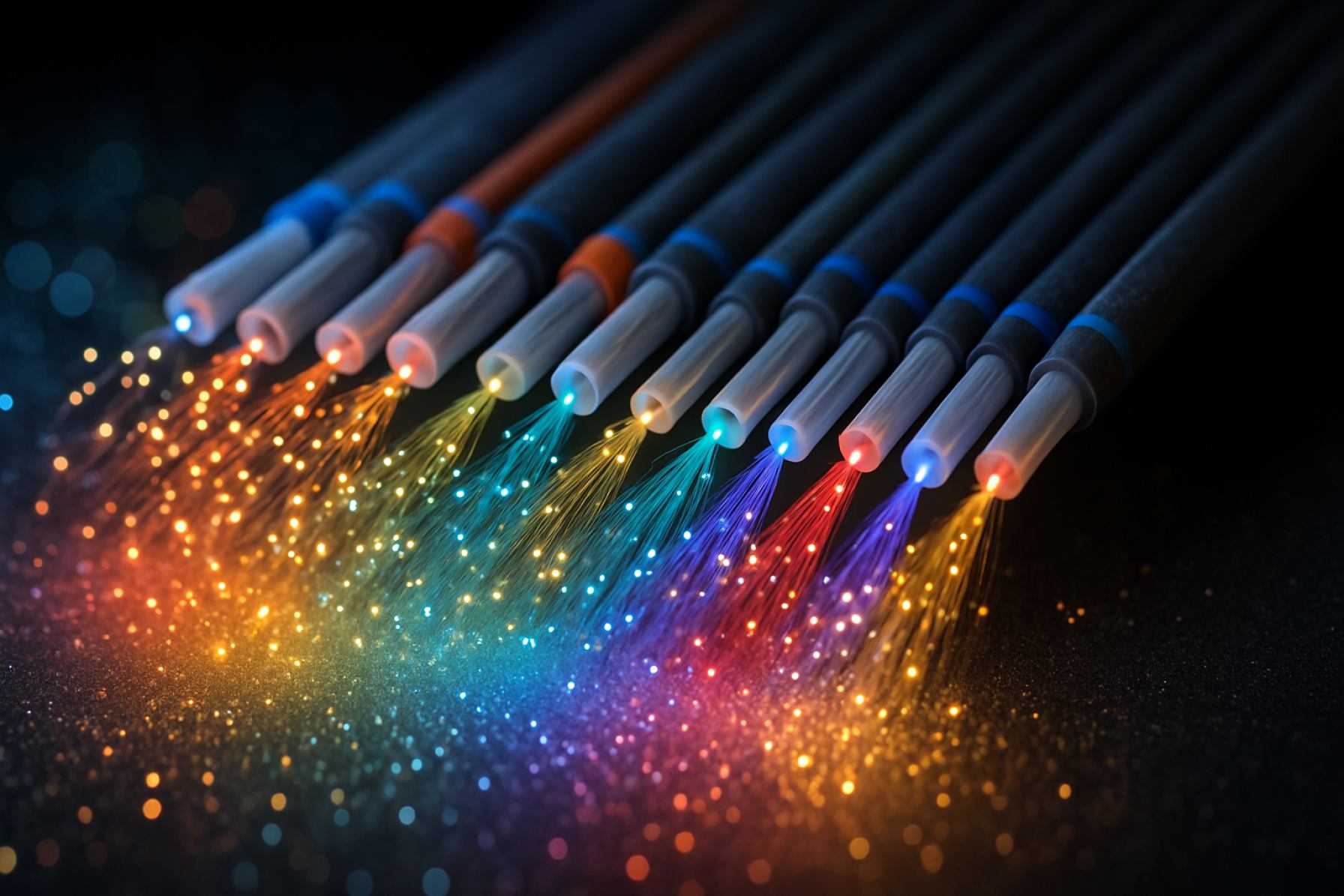
目次
- エグゼクティブサマリー:2025年-2030年の主要な発見
- 技術概観:15ファイバ光多重化システムのアーキテクチャ
- 市場規模と2030年までの成長予測
- 主要な業界プレーヤーと最近の戦略的動向
- テレコムとデータセンターにおける画期的なアプリケーション
- 多重化技術とファイバー設計の進展
- 規制および標準の状況(ieee.org、itu.int参照)
- 課題:スケーラビリティ、統合、およびコスト要因
- 競争分析:15ファイバ vs. 他の多重化技術
- 将来の展望:新興のイノベーションと投資機会
- 参考文献
エグゼクティブサマリー:2025年-2030年の主要な発見
15ファイバ光多重化システムの出現は、高容量光通信の進化における重要な転機を示しています。2025年時点では、商業およびプレ商業展開が加速しており、データ集約型アプリケーション、クラウドインフラストラクチャ、次世代無線バックホールをサポートするためのより大きな帯域幅に対する絶え間ない需要によって推進されています。これらのシステムは、単一のケーブル内に15本の並行光ファイバを使用して空間分割多重化(SDM)を活用し、従来の単一ファイバおよび少モードシステムの限界に対処する最前線にいます。
現在の15ファイバ多重化ソリューションは、主に大手光技術会社やケーブル製造業者によって発展しています。特に、NEC株式会社とフジクラ株式会社は、海を越えた距離で1ペタビット/秒を超える合計容量を持つプロトタイプおよび商用準備完了システムを示しています。これらの開発は、バックボーンインフラを将来にわたって保証しようとする海底ケーブルコンソーシアムやハイパースケールデータセンター運営者によって急速に採用されています。
2025年、主要な発見は15ファイバ光多重化の技術的実現可能性と商業的勢いの両方を強調しています:
- 容量のブレークスルー: 15ファイバシステムは、1本のケーブルで従来の単一ファイバシステムの10〜15倍の容量を提供可能で、ファイバあたり80Tbpsの伝送速度が実証されており、ケーブル全体の容量が1.2Pbpsを超えています(NEC株式会社)。
- 展開の見通し: 2026年から2028年に完成予定の新しい海底システムは、標準として12〜16ファイバペアを指定しており、15ファイバ多重化が容量、コスト、および運用の複雑さのバランスをとる甘いスポットに位置しています(SUBPartners)。
- コンポーネントエコシステム: インフィネラ株式会社やコーニング社などのベンダーからの互換性のある増幅器、多重化器、トランシーバーの入手可能性が、端から端へのソリューションを可能にし、海底および地上バックボーン全体での採用を加速させています。
- 標準化と相互運用性: ITU-T研究グループ15などの業界グループは、相互運用性を確保し、多供給者展開をサポートするための標準を積極的に開発しています。
2030年を見据えると、15ファイバ光多重化市場は堅調な成長が見込まれています。主な推進要因には、AIワークロード、ストリーミング、IoTからの指数関数的なトラフィック、持続可能でエネルギー効率の高いネットワークアップグレードの必要性が含まれます。この技術の強力なエコシステムサポートと明確な展開軌道は、次世代のグローバル通信インフラの基礎的要素となることを示唆しています。
技術概観:15ファイバ光多重化システムのアーキテクチャ
15ファイバ光多重化システムは、高容量光通信のアーキテクチャにおいて重要な飛躍を表し、世界のデータトラフィックの指数関数的成長に対応しています。従来の単一コアや少数コアの光ファイバ構成とは異なり、これらのシステムは15本の空間的に並行する光ファイバの束を利用し、それぞれが独立したまたは多重化された光信号を運ぶことができます。このアーキテクチャは空間分割多重化(SDM)に基づいており、単一のケーブル構造内で複数の空間チャネル(この場合、ファイバ)を動作させ、空間的効率と合計帯域幅を最大化します。
このシステムのコアは、マルチファイバケーブルであり、精密な幾何学的制御とファイバ間の低クロストークで設計されています。15本のファイバのそれぞれは、高密度波長分割多重化(DWDM)や、場合によってはモード分割多重化(MDM)などの高度な多重化技術をサポートでき、トータルデータスループットをさらに増加させます。これにより、長距離で複数のペタビットを超える合計容量が実現され、次世代の海底および地上バックボーンネットワークにおける重要な指標となっています。
このアーキテクチャの統合には、高度なファンイン/ファンアウトデバイス、MPO/MTPなどの高密度マルチファイバコネクタ、高度なマルチファイバ操作に対応する光増幅器が必要です。Ciena、NEC株式会社、フジクラなどの大手メーカーが、全15チャネルにわたるファイバ整合性、挿入損失、および信号の完全性の課題に取り組むソリューションを開発しています。
光増幅の進展、特にマルチコアエルビウムドープファイバ増幅器(EDFA)やラマン増幅器の開発は、これらのアーキテクチャにおける信号品質の維持において重要です。富士通やノキアは、ラボやフィールド環境でこれらのマルチファイバ互換の増幅技術を積極的に実証し、試行しています。
2025年時点で、15ファイバシステムの展開は、空間効率と将来性が最も重要な超高容量データセンター間の相互接続および海底ケーブルに焦点を当てています。国際電気通信連合(ITU)および国際電気標準会議(IEC)などの業界団体が主導する標準化の取り組みが進行中であり、相互運用可能なインターフェース、テストプロトコル、信頼性基準の確立を目指しています。
今後、15ファイバ光多重化システムの展望は明るいです。このアーキテクチャは、グローバルネットワークの次の波のアップグレードを支えることが期待されており、オペレーターにインフラストラクチャをスケールアップさせる一方で、ケーブルの量やコストの比例的な増加を求めることなく実現させるでしょう。主要サプライヤーによる継続的なR&Dおよびフィールド試験が商業化の導入およびより広範な採用を促進し、15ファイバシステムを未来のオプティカルネットワーキングの基礎石として位置付けることが期待されます。
市場規模と2030年までの成長予測
15ファイバ光多重化システムの市場は、2030年までに重要な拡大が見込まれており、これはテレコミュニケーション、クラウドコンピューティング、ハイパースケールデータセンターにおけるデータ伝送需要の指数関数的な増加によって推進されています。2025年時点では、マルチファイバ多重化は研究および概念実証から早期商業採用へと移行しつつあり、特に次世代ネットワークインフラへの大規模な投資が行われている地域で顕著です。業界のリーダーは、15ファイバシステムが超高容量光ネットワークに向けた重要なステップとなっていることを確認するために、空間分割多重化(SDM)技術を活用して単一モードファイバの物理的制限を克服しています。
現在の展開は限られていますが、主に伝説のネットワークオペレーターおよび主要なインターネットエクスチェンジプロバイダーに集中しており、バックボーンインフラを将来にわたって保証することを目的としています。NEC株式会社や富士通のような先駆者は、1ペタビット/秒(Pbps)を超える合計スループットをサポートできるマルチコアおよびマルチファイバソリューションを実証し、15ファイバアレンジメントは有望なスケーラビリティを示しています。2024年には、ノキアとファーウェイが、メトロおよび長距離ネットワークだけでなくデータセンター間の接続をターゲットにした先進的なフォトニック集積回路を使用した多重化システムの試験を発表しました。
15ファイバシステムの市場規模の予測は、より広範なSDM採用のペースに密接に関連しています。国際電気通信連合(ITU)や業界作業部会が発表した技術ロードマップによると、商業規模の展開は2028年までに10,000ルートキロメートルを超える累積設置基盤を超える可能性があり、高速道路が400G、800G、およびテラビットクラスのラインレートに移行するにつれて、30%を超える年平均成長率(CAGR)を示すと見込まれています。5G Advancedおよび6Gワイヤレスバックホールの導入に加え、クラウドトラフィックの持続的な成長が主要な需要推進要因と考えられています。
2030年を見据えて、コーニング社や住友電気工業株式会社などのメーカーは、多本数ファイバケーブルおよびサポートコンポーネントの生産能力に投資しており、15ファイバ多重化システムの世界市場価値は、10年末までに数十億ドルを超えると予想されています。光機器ベンダーとネットワークオペレーターの間での継続的な連携は、相互接続の標準化を進め、ビット当たりの伝送コストを引き下げ、大規模SDMアーキテクチャの潜在能力を完全に実現するために欠かせません。
主要な業界プレーヤーと最近の戦略的動向
15ファイバ光多重化システムの進化は、光ネットワークにおける高データ伝送容量を追求する上での重要な飛躍を示しています。2025年において、主要な業界プレーヤーは、これらの高コアカウントシステムの技術の最前線と商業展開を積極的に進めています。NEC株式会社や富士通のような企業は、マルチコアファイバ製造、空間多重化、高度な光増幅における豊富な専門知識を活用し、リーダーとして浮上しています。
2025年初頭、NEC株式会社は、グローバルキャリアとの協力により15コアファイバを用いた長距離伝送試験を成功裏に行い、このシステムがバックボーンネットワーク統合の準備が整ったことを示しました。NECの試験は数百キロメートルにわたり実施され、合計容量は1ペタビット/秒を超え、空間分割多重化(SDM)システムの新しい業界ベンチマークを設定しました。この仕事は、NECが以前に示した低クロストークおよび高信号の完全性を持つマルチコアファイバ伝送の実証に基づいており、商業規模のマルチファイバ多重化の最前線に立っています。
一方、富士通は、15ファイバシステム向けの互換性のあるトランシーバーおよび増幅器の開発に注力し、既存の光インフラストラクチャとのシームレスな統合を確保することを目指しています。2024年、富士通は12および15コアファイバケーブル用に特に設計された新しいSDM対応光モジュールのスイートを発表しました。これらのモジュールは、2025年にわたってメトロおよび長距離ネットワークのアップグレードのために主要なテレコムオペレーターによって評価されています。富士通はまた、住友電気工業株式会社のようなファイバ製造業者と戦略的提携を結び、15コアファイバの大量生産と商業展開を加速させています。
サプライヤー側では、住友電気工業株式会社とコーニング社は、予想される高コアカウント光ファイバの需要をサポートするために、R&Dおよび製造能力を増強しています。特に住友は、15コアプレフォームの幾何学と均一性を最適化する新しい製造プロセスを紹介しました。これは、コア間のクロストークと減衰を最小化するために重要です。両社は、現在アジア、北米、ヨーロッパのシステムインテグレーターとキャリアに15コアファイバのパイロットボリュームを供給しています。
今後の見通しとして、業界リーダーによるこれらの協力的な取り組みと戦略的投資は、15ファイバ多重化システムの標準化とグローバル採用を加速させると期待されています。今後数年内に、ハイパースケールデータセンター間の接続および海底ケーブルプロジェクトにおける初期の商業展開が目撃されるはずであり、相互運用性とコスト効率が向上するにつれて、より広範な採用が予想されます。
テレコムとデータセンターにおける画期的なアプリケーション
2025年、15ファイバ光多重化システムは、帯域幅の需要の増加や超低遅延によって駆動され、次世代テレコムおよびデータセンターインフラストラクチャの重要な推進者として浮上しています。これらのシステムは、複数のファイバコアまたは束を用いた空間分割多重化(SDM)を利用し、合計の伝送容量において劇的な飛躍を提供します。これはハイパースケールデータセンターやメトロネットワークにとって重要です。
重要なマイルストーンの1つは、最大15の空間チャネルをサポートする商業用マルチコアおよびマルチファイバケーブルの展開です。コリアントやNEC株式会社のような企業は、既存の高密度波長分割多重化(DWDM)プラットフォームとシームレスに統合されるSDMシステムを実証し、レガシーインフラとの互換性を維持しながら指数関数的なスケーラビリティを実現しています。例えば、NECは最近、15ファイバペアを利用したフィールド試験を実施し、合計容量が1ペタビット/秒を超えることを達成しました。これは商業システムにおける前例のない数字ですNEC株式会社。
テレコム運営者は、5Gの集中化と予想される機械間トラフィックの急増に対処するために、これらのシステムをバックボーンおよびメトロネットワークに統合し始めています。ノキアは、都市環境におけるファイバ管理の単純化と遅延の削減に焦点を当て、5Gトランスポート用の15ファイバソリューションの試験を行うために主要なキャリアと提携しています。これらの試験からの主要な性能指標には、ケーブル当たりの帯域幅が最大10倍、従来の単一ファイバシステムと比較してスペース要件が40%削減されることが含まれていますノキア。
データセンター環境では、GoogleやAmazon Web Services (AWS)のようなハイパースケーラーが、東西トラフィックの最適化のために光部品製造業者と協力して15ファイバ多重化を試験しています。これらの展開は、AI/MLワークロードや大規模データの複製に伴うボトルネックを緩和することを目的としており、より高いスループットとエネルギー効率の向上を提供します。開発ロードマップによると、互換性のあるトランシーバーの量産は2026年末までに見込まれており、新世代のファイバコネクタとの相互運用性に焦点を当てていますCiena。
今後、15ファイバ光多重化システムの展望は強いままです。800Gおよび1.6Tイーサネット標準への継続的なプッシュに加えて、エッジコンピューティングインフラストラクチャの集中化が2027年までの主流の採用を促進する可能性があります。Open Compute Projectが開始したような業界アライアンスは、標準化とエコシステムの発展を加速させ、テレコムおよびクラウド領域全体でこれらの画期的なアーキテクチャを強力にサポートすることが期待されています。
多重化技術とファイバー設計の進展
15ファイバ光多重化システムの開発は、高容量光通信ネットワークの進化において重要な飛躍を示しています。世界的なデータ需要が加速する中で、ネットワークオペレーターや機器メーカーは、従来の単一コア、単一モードファイバを超えて容量をスケールさせる戦略として空間分割多重化(SDM)にますます注目しています。15ファイバシステムは、ケーブル内に15本の並行コアまたはファイバを束ね、2025年およびその近未来におけるSDMの研究と展開の最前線であるといえます。
いくつかの業界リーダーがこの分野で顕著な進展を遂げています。NEC株式会社は、マルチコアおよびマルチファイバ技術を用いたフィールド試験が成功裏に行われ、SDMケーブル上で1ペタビット/秒を超える伝送容量を実現したと発表しました。これらの試験では、最大16ファイバを含むケーブル設計を利用し、海底および地上アプリケーション向けに15ファイバシステムの技術的実現可能性を強調しています。同様に、住友電気工業株式会社は、低クロストークと高密度を備えた超高ファイバカウントケーブル(16ファイババリアントを含む)を開発し、全チャネルでのパフォーマンスの完全性を維持するために、先進的なファイバリボンおよびコーティング技術を採用しています。
機器側では、フジクラ株式会社は次世代の多重化スキームをサポートするための高密度ファイバおよび接続ソリューションを商業化しています。これらのソリューションは、12本から16本のファイバリボンの効率的なスプライシング、カップリング、および管理を可能にし、コアおよびメトロネットワークにおける15ファイバシステムの展開を直接促進しています。また、コーニング社は光ファイバ設計におけるイノベーションを導入し、減衰が少なく、曲げに強いファイバに焦点を当てており、密集したマルチファイバ配置にとって重要です。
今後、15ファイバ多重化システムの展望は堅調です。ITU-Tおよび他の標準化団体はSDM対応のファイバおよびケーブルの仕様を進展させており、これにより相互運用性がスムーズになり、2026年までの商業的採用が加速すると期待されています。NEC株式会社や住友電気工業株式会社が関与するコンソーシアムが発表した主要な海底ケーブルプロジェクトでは、マルチファイバSDMデザインを導入し、海を越えるデータルートをターゲットにしています。ハイパースケールデータセンターおよび5G/6Gバックボーンがますます高いスループットを要求する中で、15ファイバ光多重化は主流のソリューションになることが期待されており、明日のグローバルネットワークのスケーラビリティと耐障害性を確保しています。
規制および標準の状況(ieee.org、itu.int参照)
15ファイバ光多重化システムの規制および標準の状況は、高容量光伝送の需要の高まりやデータ集約型アプリケーションの急増に応じて急速に進化しています。これらのシステムは、複数の光ファイバを介してデータストリームを同時に伝送することを可能にし、次世代光ネットワーキングの最前線に位置しています。2025年時点及びその後の数年間において、業界標準団体および国際規制機関は、マルチファイバ多重化ソリューションの技術的進展および実装要件に対応するため、フレームワークを積極的に更新しています。
IEEEは、光伝送システムの技術標準の策定において中心的な役割を果たしています。イーサネット標準を管理するIEEE 802.3作業グループは、歴史的に並列光学ソリューションに関する仕様を扱ってきました。しかし、15ファイバ多重化の出現に伴い、IEEE内部では従来の標準を拡張するか、新しいプロジェクトの承認を導入して高いファイバカウント、チャネル管理、および相互運用性の要件をカバーすることについて議論が進行しています。これらの取り組みは、新しいマルチファイバシステムがレガシーインフラストラクチャにシームレスに統合でき、高スケールを確保できるようにするために特に重要です。
国際的な舞台では、国際電気通信連合(ITU)が光輸送標準の調和において重要な役割を果たしています。光輸送ネットワークおよび技術を担当するITU-T研究グループ15は、単一モード光ファイバの特性に関するG.652および波長分割多重化アプリケーションに関するG.694などの推奨事項を積極的に見直しています。2024年末から2025年初頭にかけて、ITU-T内の作業部会が、新しい技術報告書や改正を行うための協議を開始し、ファイバの識別、チャネルマッピング、運用管理など、マルチファイバ、密集型多重化の具体的な課題に対処しています。これらの改訂は、15ファイバシステムがパイロット展開からより広範な商業展開へ移行する際に、ベンダーや国の間での相互運用性を支援するために重要です。
今後は、IEEEとITUが業界の利害関係者との協力を強化し、物理層仕様だけでなく、マルチファイバ環境におけるネットワーク管理、セキュリティ、そして自動化に関する包括的な標準を確立することが期待されます。15ファイバ光多重化システムが今後数年間で普及するにつれて、これらの進化する規制および標準フレームワークへの準拠は、グローバルな相互運用性、システムの信頼性、および多様なネットワーク環境での展開を円滑に進める上で不可欠です。
課題:スケーラビリティ、統合、およびコスト要因
15ファイバ光多重化システムの展開は、バックボーンネットワークの容量を指数関数的に増加させる手段として注目を集めていますが、2025年および今後の数年間において、スケーラビリティ、シームレスな統合、そして受け入れ可能なコストプロファイルを確保するためにいくつかの主要な課題に取り組む必要があります。
スケーラビリティは、ネットワークオペレーターが従来の単一および数ファイバのソリューションを超えて拡張を図る際に大きな障害となっています。15本の並行ファイバ間での信号の完全性を管理し、特に高データレートかつ長距離でのクロストークを最小限に抑えるためには、高度な多重化/デマルチプレクサハードウェアと洗練されたデジタル信号処理が必要です。NEC株式会社やノキアのような企業は、複数のファイバパスを持つ高度なSDM(空間分割多重化)システムを実証していますが、生産環境での15ファイバへのスケーリングはフットプリント、電力消費、およびネットワーク管理の課題を強めます。
既存のネットワークインフラとの統合は、もう一つの大きな懸念です。現在の世界の光ネットワークのほとんどは、単一ファイバまたは制限されたマルチファイバアーキテクチャに基づいています。15ファイバシステムの導入には、新しいケーブル、コネクタ、および互換性のある増幅/再生機器の展開が必要です。レガシーシステムとの相互運用性および後方互換性を確保することは容易ではありません。Cienaやインフィネラによる業界の取り組みは、オープンネットワーキングとモジュラー伝送装置ソリューションに焦点を当てていますが、15ファイバレベルでの統合にはさらなる標準化や業者間の協力が必要です。
コスト要因は依然として重要な問題です。15ファイバケーブルの展開に伴う資本支出は、従来の展開に比べて大幅に高く、新たに関連する多重化器、増幅器、制御システムも同様です。さらに、メンテナンスの複雑さが増し、より高度なモニタリングが必要になることで、運用費用も上昇します。コリアント(現在はインフィネラの一部)やフジクラなどのサプライヤーは、統合や大量生産を通じて部品コストを削減するために取り組んでいますが、広範な導入にはさらなる価格削減と有意義な総所有コストの利点が必要です。
今後、これらの課題に取り組むためには、機器メーカー、標準化団体、およびネットワークオペレーター間の継続的な協力が必要です。ITU-T研究グループ15のような業界コンソーシアムが、2025年以降、高容量光輸送システムに関するマルチファイバのインターロペラビリティ標準やベストプラクティスの開発において重要な役割を果たすと期待されています。
競争分析:15ファイバ vs. 他の多重化技術
15ファイバ光多重化システムは、高容量光通信のための空間分割多重化(SDM)分野において重要な進化を示しています。単一のケーブル内に15の並行ファイバパスを利用することで、これらのシステムは従来の単一ファイバまたは少モード多重化ソリューションに比べて合計データスループットを劇的に増加させることができます。ネットワークオペレーターやハイパースケールデータセンターが急増する帯域幅需要に対応しようとする中で、15ファイバソリューションと高密度波長分割多重化(DWDM)やマルチコアファイバ(MCF)などの他の多重化技術との競争環境が急速に変化しています。
2024年から2025年の最近の展開やフィールド試験によると、15ファイバシステムはケーブルあたり1Pb/sを超える合計容量を提供できることが示されており、これは従来のSDMまたはMCFシステム、通常は4〜7コアまたは空間チャネルを採用しているものよりも大幅な改善です。例えば、NEC株式会社は、高カウントの空間多重化を統合した海底ケーブルシステムを実証し、並行ファイバ設計が研究段階から商業的準備段階に移行しています。同様に、住友電気工業株式会社は、高ファイバカウントケーブルの製造可能性と信頼性を強調し、海底および地上のバックボーン展開に適していると述べています。
直接比較すると、DWDMは単一ファイバでの容量を最大化するための従来の技術であり、各コアに数十の波長を利用しています。しかし、100波長を超えるファイバにおける非線形障害、スペクトル効率、コストのスケーリングに関する制約から、空間分割多重化がますます魅力的になっています。15ファイバシステムは、物理的にチャネルを分離することによって、マルチコアファイバに対して増幅を簡素化し、クロストークを減少させ、特に超長距離ルートにおいてDWDMのいくつかの課題を回避します。
競争の観点から、コリアント(現在はインフィネラの一部)やノキアなどの主要なサプライヤーは、DWDMおよび統合されたSDMソリューションの進展を図っていますが、従来の多重化のスケーラビリティの限界に対処するために、並行ファイバアーキテクチャへの投資も行っています。一方で、ケーブルやコンポーネントメーカーは12本以上のファイバカウントの生産能力を増強し、2025〜2027年のネットワークオペレーターのロードマップをサポートし、15ファイバ束の展開の経済性を向上させようとしています。
今後、15ファイバ光多重化の採用は加速すると予想されており、特に海底ケーブルプロジェクトやメトロ/地域のバックボーンにおいて、ケーブルあたりの容量を最大化することが重要です。業界リーダーが指摘しているように、ファイバ管理、接続化、システム統合に関する技術的なハードルは積極的に対処されており、15ファイバシステムがMCFや先進的なDWDMソリューションに対して強力な競争相手となることが期待されています。
将来の展望:新興のイノベーションと投資機会
光通信の環境は急速に発展しており、15ファイバ光多重化システムが超高容量伝送の最前線を代表しています。2025年に入るにあたり、スケーラブルでエネルギー効率が高く、コスト効果の高い光インフラストラクチャへの移行が加速し、単一のケーブル内に15本の空間的に離散したファイバを通じて並行伝送を利用するシステムの研究やプロトタイピングが進んでいます。この戦略は、データセンターの相互接続、クラウド、AIのニーズを満たすための合計データレートの劇的な増加を約束します。
最近の試験は、空間分割多重化(SDM)、コンパクトマルチコアファイバ(MCF)、および高密度フォトニックインテグレーションの進展を活用した15ファイバ多重化の技術的実現可能性を示しました。NEC株式会社やノキアは、伝統的な単一モードの枠を超えてスケールできるマルチファイバシステムの展開を検証するために、グローバルなテレコムキャリアと積極的に連携しています。2024年には、住友電気工業株式会社が、レコード低減衰を持つ15コアファイバの開発を発表し、各コアに対してテラビット/秒の伝送を可能にし、実用的で商業用の実装への道を開きました。
投資の観点から、今後数年間では、高精度のファイバ製造、接続化、SDM対応トランシーバ技術における製造能力への資金が増加すると予想されます。フジクラ株式会社やコリアントは、大規模なSDMをサポートするためにポートフォリオを拡大しており、Cienaは、マルチファイバのルーティングとネットワーク管理の複雑さに対応するために設計された次世代光輸送プラットフォームに注力しています。
2025年から2027年までの展望では、15ファイバシステムの統合はフィールド試験から初期の商業展開へと移行すると期待されており、特にデータ需要が爆発的に増加している地域において、海底および地上のバックボーンにおける展開が行われる見込みです。国際電気通信連合(ITU-T)などの業界組織は、相互運用性を促進し、ファイバの整合性、クロストーク軽減、スケーラビリティの課題に対処するための標準を実施しています。競争環境は、SDMに特化したファイバ、増幅、デジタル信号処理を網羅するエンドツーエンドのソリューションを提供できる企業に有利になるでしょう。
要約すると、15ファイバ光多重化システムは研究から実用展開への移行の瀬戸際にあり、技術的なブレークスルーと戦略的な投資の両方によって強い推進力が得られています。今後数年は、採用のペースとグローバルデジタルインフラを支える高容量光ネットワークの形状を決定する上で重要な期間となるでしょう。
参考文献
- NEC株式会社
- SUBPartners
- インフィネラ株式会社
- ITU-T研究グループ15
- Ciena
- 富士通
- ノキア
- ファーウェイ
- 住友電気工業株式会社
- コリアント
- Amazon Web Services (AWS)
- Open Compute Project
- IEEE



